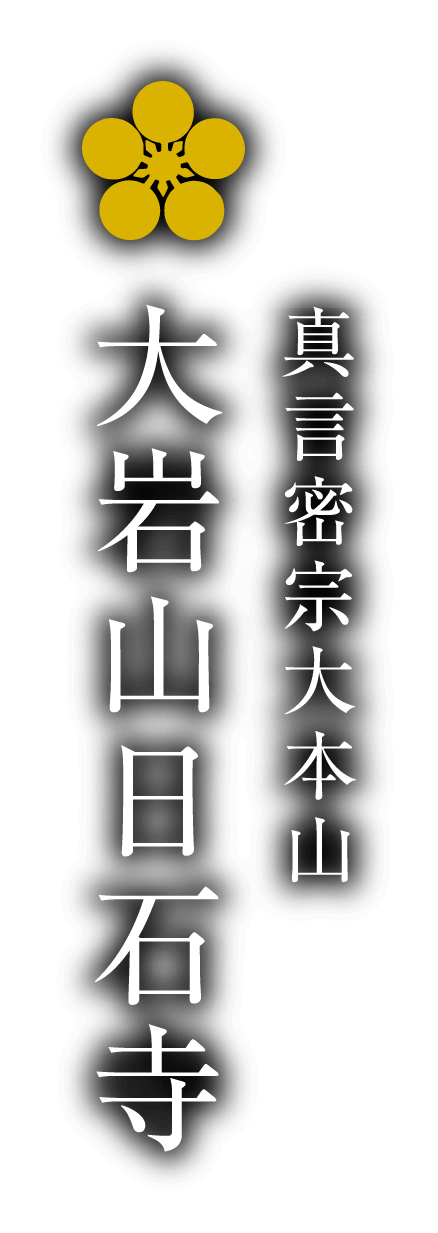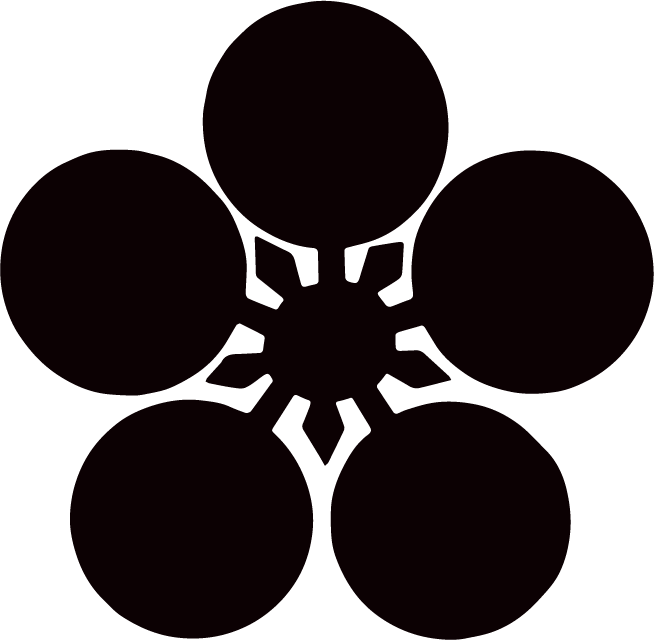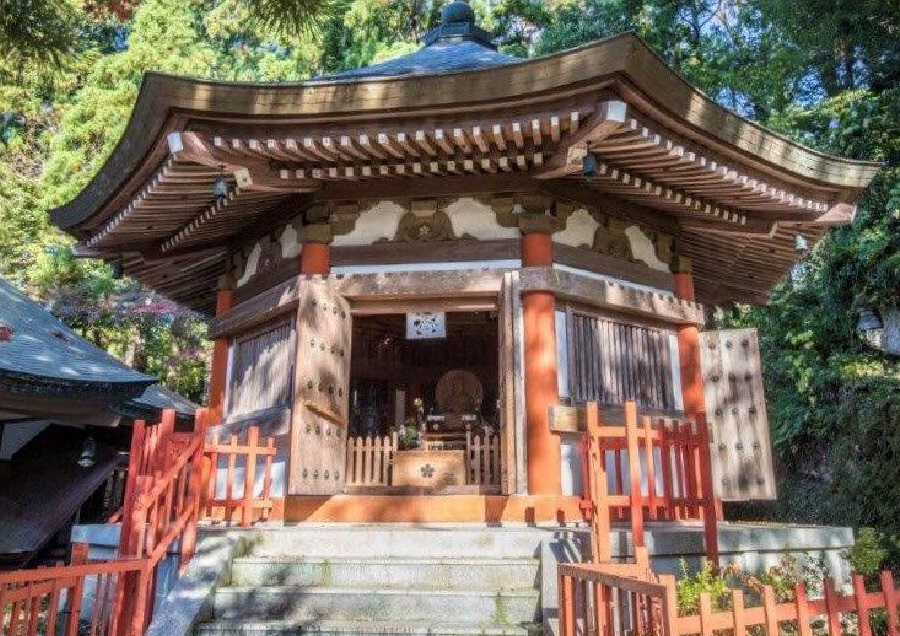フォトギャラリー Gallery
お知らせ News
アクセス Access
真言密宗大本山大岩山日石寺
〒930-0463
富山県中新川郡上市町大岩 163
tel.076-472-2301
fax.076-473-2221
- ■富山地方鉄道上市駅から車で約 10分
- ■富山地方鉄道上市駅から
町営バス柿沢・大岩行で約 25分
(本数が少ないため要確認) - ■北陸自動車道立山ICから車で約 15分
駐車場: 100台
駐車料金:無料